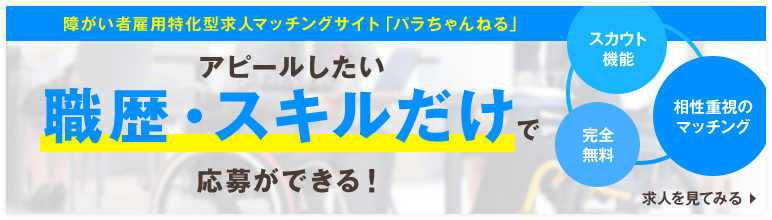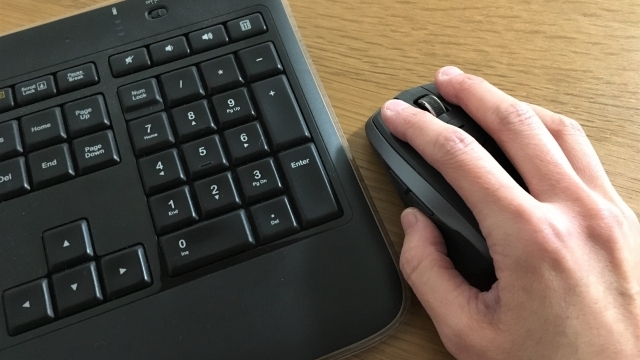16歳の時に飛び降り自殺を図り頸髄を損傷。以後車いすに。障害を負ったことで生きづらさから解放され、今は小さな温泉街で町の人に支えてもらいながら猫と楽しく暮らしている私が振り返る、働くってなに?障害者差別ってなに?生きることの価値ってなに?
母と私の初めての職場
母はチェーン店のレストランで長年勤めている。その前は自分で焼肉屋を経営していた。アルバムを開くと骨付きカルビをおしゃぶり代わりに、働く母の背におぶわれている私の写真がある。
母は飲食に関わって数十年の腕利きのベテランだ。とにかく働き者で、ほとんど家にいたことがない。そんな母と、中卒で車いすの重度障害者な上、働いた経験のない19歳の私の時給が同じ。
座る暇もなく必死に働いても、残業代も殆ど出ない母と、急な体調不良で時間よりも早く帰ったり、職場のトイレを利用するのに別の職員の手を借りたりしている私。
働くことへの葛藤と母への想い
私が18歳の頃に勤めることになった自立生活センターは、障害者が街で自立生活をするためのサポートをする。私もまた、職員でありつつ、サポートされる側でもあるから、障害者への配慮が広がればいいと謳う中で、しかし、母の労働環境とのあまりの差に、ここまで手厚くされてもいいのだろうか、これで自立して働いていると胸を張っていいのか、という思いが当時の私には拭い去れなかった。
その上、20歳になると障害年金がもらえるようになる。明らかになんの生産性のない自分が、母と同じくらいの給料をもらい、さらに年金を受け取ることができるということに違和感と強い罪悪感を覚えた。
自立への挑戦と挫折
それだけたくさんのお金をもらい、毎日ヘルパーに生活を支えてもらっている自分が、障害者差別を社会に訴える。なんだかそれはあまりにも都合が良過ぎはしないか?
荒れてあかぎれだらけの母の手を知っているだけに、自分の手がきれいなままなのが、許せなかった。

ついぞこの間まで健常者として母子家庭に暮らし、奨学金をもらいながら高校に通うも、貧しい生活の中で母から要求された難関大学進学への重圧に耐えきれずに飛び降り自殺を図った私にとって、あまりに大きな自己矛盾をはらんでいた。これはもはや、逆差別なのではないか。私は自立生活を始める際に職場の代表から貸してもらったお金を返し終えたあと、センターを辞職した。
健常者と同じように働きたいと思った。
自分にはそれができるはずだ、と。
ハローワークで求職していると、健常者向けのCGとWEBデザインを学べる職業訓練の募集を見つけた。運のいいことに、自宅すぐ近くに教室があり、車いすでもどうにか通えそうだった。
パソコンの作業なら、私の場合、健常者と遜色ない。デザインであれば、場合によってはフリーランスとしても働くことができるだろうと、早速応募し、4ヶ月間通うことになった。
カリキュラムについては何も問題なく、順調に技能を習得していった。ところが通い始めて2ヶ月経った頃から、原因不明の高熱が出るようになり、急遽入院することに。
腹膜炎だったようだが、体の麻痺のせいで痛みがわからず、正確な診断が出るまでに一ヶ月もかかった。その間は毎日40度近い熱が出ており、適切な治療が始まる頃には腸閉塞となってしまっていた。出席日数が足りなくなって修了できないことを恐れた私は、その間何度も退院させてくれるよう頼んだ。
社会からの疎外感
「もしあなたが私の娘なら、絶対安静するように言います。君は痛みがわからないようだが、本来なら激痛のはずだ。下手すると死んでしまうよ」
そう主治医に言われ、泣く泣く諦めた。実際、痛みはわからないものの、かなりしんどかった。
結局、修了は叶わず、また、訓練校が斡旋する企業に、車いすの人間が就職できる職場はやはりなかった。
「障害者として働くのは甘えだから健常者のように働きたい」なんて、傲慢な考えだった。
健常者と同じように働くことの難しさ
そもそも、障害が理由で高校に復学できず、高卒認定試験に受かっても同じ理由で大学にも行けず、ならば就職だと思ってハローワークに行っても「車椅子の人間が働ける職場はない」と一蹴され、ようやく見つけたのが自立生活センターだったのだ。
十分、障害者差別を受けていたわけだが、頑張ればなんとかなると思い込んでいた私はこのあたりまでピンと来ていなかった。差別されている自覚がなかった。
けれど、自立生活センターに戻る気にはなれなかった。私の思う「働く」とは違うという確信があった。
障害者就職説明会に履歴書を書いて持って行ったが、車いす対応の職場は2社しか無く、どちらも自宅からは通えそうになかった。
自分の価値と働く意味を問い直す
飛び込みで何かできることはないか、聞いて回ると、とある一社の社長さんが履歴書を見て頑張りを認めてくれ、自分も中途障害で仕事を失い、起業したのだと話してくれた。ご厚意で不定期ながら自宅でできる仕事を回してくれるようになったが、それだけでは食べてはいけない。
自分は社会から求められていない、というのが、かなり堪えた。
「君もいつか起業しなさい」と社長は励ましてくれたが、ほとんど社会経験のない自分には自信がなかった。

生きる価値と働くことの本質
働くってなんだろう。じわじわと貯金を食いつぶしていく中で考えた。労働者になるために(できればより待遇の良い企業でより良い給料をもらうために)必死に勉強してきた。誰かに選んでもらうために、評価され、見合った対価を得るために。
「君たちはまだ若い。無限の可能性に満ち溢れている」とポエムのような(ポエムに失礼)美辞麗句を気持ちよく連ねる高校教諭。親の収入と自分の成績を見れば、高校生に夢も希望もないことなんて一目瞭然だ。大学受験という現実が差し迫る中、夢なんておちゃらけたことを言ってられる高校生なんてどこにいるだろう。毎日絶望の淵を歩かされているような気分だった。そして、その淵から転げ落ちた。
その転げ落ちた暗闇の底で「車いすで働ける仕事は有りません」ときっぱり言いつつ、「好きなことは何?まずはやりたいことを見つけたらどう?」と宣ったハローワークの職員。生きるためには好きも嫌いも言ってられないし、そもそも仕事なんて無いじゃないか。
誰かに選ばれるための努力とその限界
なんだかこれって、受け身な生き方だ。誰かに気に入られたい。認められたい。そのためには誰よりも努力すればいいのだと思っていた。
けれど誰も、私を見てくれない。努力が足りないのか、それとも、私に価値がないのか。それは違う、と思った。間違っている。その考え方では命がいくつあっても足りない。
実際に私は二度も死ぬ思いをしたのだ。そう、「価値がないなら、生きる意味なんて無い」と16歳の私は飛び降りたのだった。
自分の価値を他人に委ねない生き方
所属がないことに怯えたのは、何者でもない自分に自信がないから。どうして自信がないのだろう。私は一体誰に認められたかったのか?
選ぶ側の人間とは、一体誰なのか。対価を、賃金をくれるのは誰なのか。その人達の基準で、私の価値を決められていいのか。その人達のために私は生きているのか。違う。
生きる意味と価値の再定義
そもそも、生きる意味なんて無い。「生きているだけで価値がある」なんて、それも嘘だ。人の命に価値など無い。「価値」というもので計ってはならない。それでいいのだ。ならばもう、好きにやるしかない。拾った命だ、使い込んでやれ。そう決めた。