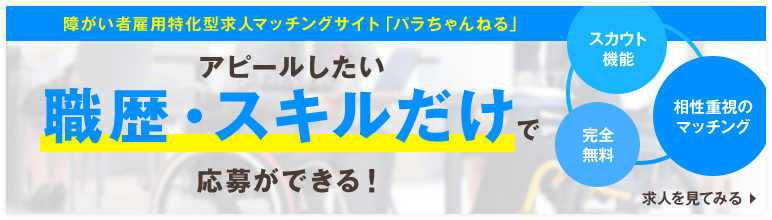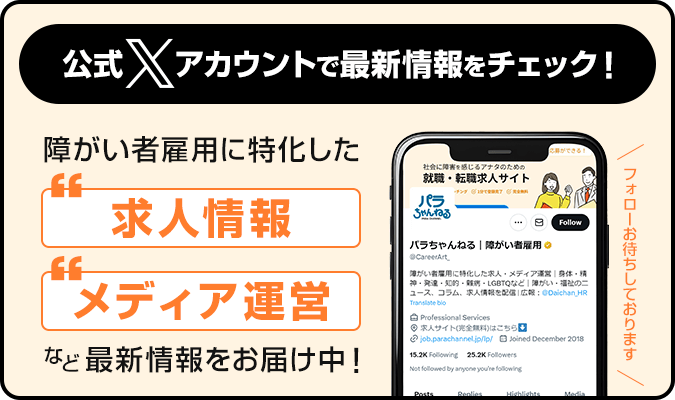私には二人の子どもがいますが、上の子は今年で小学一年生になりました。保育園時代にはなかった夏休みがやってきて、障害特性と仕事内容から在宅ワークを選んでいる私にとって、いつもとは違う考え事が発生しました。今回は、今年小学生になった6歳さんと、両親ともに在宅ワーカーという我が家の夏休みの過ごし方について少しお話したいと思います。
6歳の夏休みデビューと在宅ワークのバランス
こんにちは、とくらです。
皆さん、今年の夏はどう過ごしましたか?正直、私はあまりの暑さにほとんど出歩かない毎日を送りました。
私には二人の子どもがいますが、上の子は今年、小学一年生になりました。小学校に上がったことで、保育園時代にはなかった夏休みがやって来ました。
「初の夏休み、どうやって過ごそう」と考えると、あまりの不安で夏休みが近づくとどんどん眠れなくなっていったほどです。
さて、今回は、今年小学生になった6歳さんと、両親ともに在宅ワーカーという我が家の夏休みの過ごし方について少しお話したいと思います。
夏休み開始前の懸念

夏休みが始まる前、私は主に以下のような不安がありました。
- 宿題をまったくやらないのでは?
- 私も夫も仕事にならない説
- お昼ご飯作らないと駄目かい?
- そもそもなんで学童予約しなかったんだろ…
コロナでの休園期間を経たとはいえ、一か月半もの間、夏休みなのにずっと仕事をしている両親と一緒に過ごすというのはきっと長子にとってストレスフルなはず。
その上、小学校だと「夏休みの宿題」なるものも出ます。自分の子どもの頃を思い返すと、宿題なんて最終日に夜更かしして終わらせるものでした。果たして、子どもは宿題をやってくれるのか。
子ども自身だけでなく、私の生活も変える必要があるかもしれません。普段のお昼ご飯は夫と二人なので特に気にする必要はありません。食べたり食べなかったり、適当なカップ麺だったり、時々ランチに出かけたりと自由にしていましたが、ここに子どもが一人加わるとなんだかちゃんとする必要がある気がしてきます。
ああ、何で我々は学童を予約しなかったのでしょうか…。「家に人がいるのに学童に預けるのは可哀そうだ」という夫の意見を採用しましたが、始まる前から夏休みへの恐怖で押しつぶされそうでした。
とにかく小学生は暇を持て余している
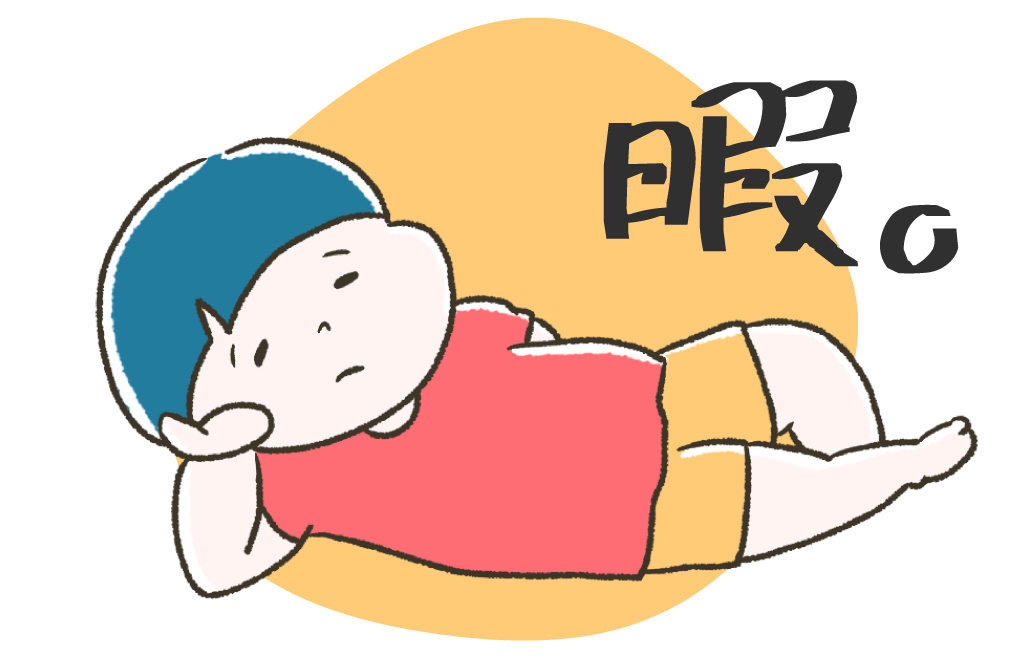
夏休みが始まると、すぐに6歳児は暇を持て余し始めました。
- 毎日行きたい公園
- スマホ、ゲーム、テレビ…そんなに長時間もたない
- 朝早い!
夏休み中の子どもがやらなければいけないことと言えば宿題ですが、それもそこまで時間はかかりません。プリントで出された宿題は初日に終わってしまったため、2日目以降は1日10分のアプリ学習が残されたのみ。
本人は毎日公園に行きたがるものの、今年の暑さでは熱中症などの心配もあり、さすがに昼休みに毎日公園に行くわけにもいきません。(おまけに登校日のプールも、ほとんど暑さのために中止になってしまい、更に暇が加速…)
子どもが一人で家でできる遊びと言えば、スマホ、テレビ、ゲーム、読書などがありますが、それも長時間はもちません。外で体を動かすことに比べればあまり魅力的ではないようで、体力を持て余していました。
公園や学校に行けず、日中に走り回ることもなくなったため、夏休み前よりも1時間以上早く起きてくるようになりました。
とにかくやることがありません。しかも早起きで一日が長い…。
両親の仕事中はひたすらに周囲をうろうろしたり、公園に誘ったり、「暇!」が全身から溢れています。
なんとか気を紛らわせようと、プラモデルを作ってみたり、図書館に行ったり、土日や会社が休みの日は一緒にジムに行ったりと手を変え品を変え飽きさせないようにする必要がありました。
救いだったのは、私の両親が夏休み中かなりの頻度で子どもを連れだしてくれたこと。これがなければ、6歳さんの4月から鍛えてきた小学生パワーが爆発して手が付けられなかったことでしょう。ありがたい…。
宿題という強敵
さて、ほとんどの宿題は一人で終わらせてくれたのですが、まだ強敵が残っていました。それは、必ずと言っていいほど小学生の夏休みの宿題に組み込まれている自由研究。自由研究は「どうぞ一人でやってください」というわけにはいかず、どうしても親が関与する必要があります。
自由研究は第二子(3歳)がいる土日や、仕事中に行うのは難しいと判断し、夫が1日有休を取得して仕上げていました。もっと上手く乗り切る方法が知りたい…。
また、読書感想文や絵日記など、感想やできごとのまとめ文章を書くという作業も親子で苦戦。6歳さんは普段から自作の絵本を描いたり、お手紙を書いたりと、文章を書くこと自体には抵抗がなかったのですが、形式の決まった文章を作ることに慣れていなかったのです。
文字は書けてはいるのですが、まだまだマスの中にきれいに納めて書くことも苦手だったので、ひらがなと漢字の練習ドリルで練習するところから始まりました。自由課題への道のりは長いのです…。
ドリルを見て、書き方を教える作業も仕事の合間、休み時間など、短時間でなんとか対処していかなければならないのも大変でした…。
一方、毎日取り組む必要のある宿題がタブレットに配信されるシステムだったことはとても助かりました。タブレットだと、プリントを無くしたり、ドリルの何ページが指定されていたか分からなくなったりするようなことがないからです。
私が小学生の頃は出された宿題を全て発見するのにかなりの時間を要していたように記憶しています。この時間が無くなるだけでも本当に子どもたちのストレスが軽減されるのではないでしょうか。
プリント学習で紙に書き、タブレットの宿題で電子機器の扱いに慣れる。どちらも経験できる現代の子どもたちの宿題には「令和だなあ」と感じました。
短時間でも毎日お散歩に行こう
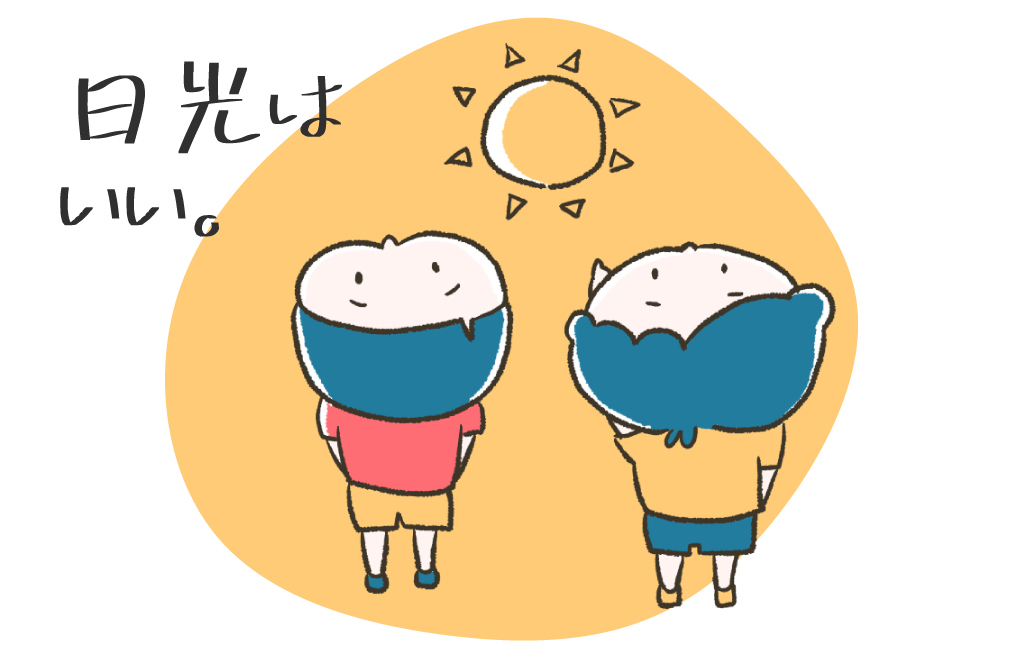
なかなか苦労が絶えない夏休みですが、一緒に過ごして良かった点もあります。ラジオ体操に一度も参加したことのない小学生だった私が、なんと今年は子どもと一緒に皆勤賞をとれたのです。(とはいっても、我が家の町内会では1週間しか開催されないというショートなものでしたが…)
「ラジオ体操に間に合うため」という目的があったからか、6歳さんも素早く着替えができるようになり、ずいぶん朝の支度に時間がかからなくなりました。
また、朝の15分程度の時間とはいえ、体を動かすことで6歳さんの運動不足も多少解消された様子。
「今年はあまりにも暑いのでなるべく外出しない」という方針でしたが、とにかく外に出たい小学生に納得してもらうには、短時間でもいいので外に出るしかありませんでした。「来年からは暑さ対策に気をつけながら、短時間でも外に出よう」と思いました。
まとめ
開始前に危惧していたほどではありませんでしたが、毎日暇で仕方ない小学生と過ごす夏休みはなかなかにハードでした。
未就学児のようにお昼寝をさせるわけにもいかないので、常時「何かをさせなければならない」という焦りで仕事中も謎の緊張感がありました。来年はできれば学童クラブの活用を検討したいところですが、夫とバチバチに話し合う必要がありそうです。
障害特性と仕事内容から在宅ワークを選んでいますが、この長期休みはいつもとは違う考え事が発生するので、要注意です。
次の子どもの長期休みである冬休みを迎えるにあたって覚えておきたいことは4つ。
- 本をとにかく大量に用意しておく
- 一人でできるお手伝いで時間を潰させる
- 毎日短時間でも散歩に行く
- お昼ご飯は全て弁当に
親子どちらにとっても、ストレスの少ない日々を送れるようにしていきたいものです。