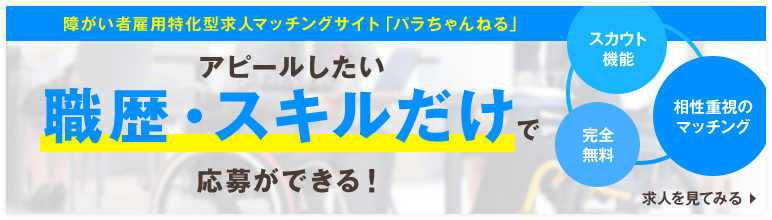16歳の時に飛び降り自殺を図り頸髄を損傷。以後車いすに。9月16日に「しにたい気持ちが消えるまで」という書き下ろしエッセイを出版した。今回は出版社からお声かけいただいたところから、1年以上かけて出版されるまでを振り返る。
本の執筆依頼の連絡が入った
「自己肯定をテーマに書き下ろしで本を書いてみませんか」というメールが届いたのは、2020年の10月のことだった。
突然の夢に見た商業出版の依頼に、嬉しさよりもまずは疑う気持ちのほうが優った。もしかしていたずらではないだろうか?
スマホで出版社の名前を検索する。三栄。実は聞いたことのない出版社だった。
調べてみると、『男の隠れ家』や『FUDGE』など、書店の雑誌コーナーで見かけたことのある名前が目についた。車やバイク、モータースポーツなど、男性向けの雑誌を多く出しているとこか…。
私はふと、障害者施設にいた頃に、同じ障害を持ったバイク好きのおじさんが楽しみにしていたバイク雑誌の袋とじを思い出した。そこには、ほとんど下着のようなピタピタのライダースーツを身に纏った綺麗なお姉さんが大きなバイクにまたがりながらおっぱいを露出しているグラビア写真が並んでいた(※三栄さんの雑誌ではない)。
編集者の人が見てくれたというTV番組で自分が下ネタを披露したこととそれとが重なり、もしかして、よくある(?)グラビアページのあるような自伝を出すことになるのだろうか、という一抹の不安が頭をよぎった。
んなアホなと妄想をかき消しつつ、いや、しかし万が一にもそういうことがあるかもしれないと警戒は緩めないようにしつつ、依頼の詳細を教えてほしいとメールを打つ。
するとすぐに丁寧な返事が返ってきた。まだ漠然とはしていたが、「豆塚さんが書きたいこと、表現したいこと、これまで書かれたことを聞かせてほしい」とある。どうやらそういう依頼ではないようだ。ホッ。言葉は人を殺すこともあり、救うこともある、と前置きしながら、「豆塚さんの言葉に希望を感じた」と書いてくださり、心が動いた。
リモートでの打ち合わせのときの感情

まずは打ち合わせをしましょうと、当時はまだ慣れていなかったリモートで恐る恐る接続すると、画面には化粧気のないショートヘアの女性が映った。着心地の良さそうな生成りのリネンのシャツをふんわりとまとっている。
もらったメールの文面のように丁寧な言葉をゆっくり淡々と喋るMさんは、正直なところ、男性向けの雑誌をたくさん出している出版社のイメージからは程遠かった。
中性的、というにもちょっと違う、あまり「性」そのものを感じさせない、飾らない雰囲気が心地よく思え、緊張がほぐれた。
生きることがしんどい人が読んで少し楽になったり、お守りのように読める自伝エッセイ。正しさだけでなく、理想と感情や欲が矛盾する部分も表現できているもの。打ち合わせではそのくらいの方向性が決まった。
とりあえず今月いっぱいで書けるところまで書いて送ってみてほしいとのことで、改めてパソコンの前に座ってみた時に、「それって実は一番難しいのでは…」と悩むこととなった。
実は「こういう本にしたい」という、ある程度の本のイメージは頭の中にあった。ずっと手元に置いておきたくなる、何度でも読み返せる、お守りみたいな本。自身で詩集を作る時にいつも意識することだ。
けれども、「自伝」でそれができるだろうか。個人的な体験、しかも自分の経験したことは、きっといわゆる「普通」からは遠く離れている。
顔も名前も晒している私が「体験談」として語るとき、あまりにも「豆塚エリ」が前面に出て、生々しい体験や感情が曝け出され、読者が引いてしまうこと、共感よりも「自殺はしてはいけない」だとか「みんな違ってみんないい」みたいなお題目が感想に上がってくるようなものになるのはどうしても避けたかった。
言葉は乾いていないといけない。構成は結晶のように美しくなければいけない。
けれども、生きづらさをなくすためのメソッド本のようにはしたくなかった。「自分を愛しましょう」「完璧主義をやめましょう」「嫌な誘いははっきり断りましょう」なんて言われてそれができるなら既に誰だってやっているだろう。それにはやはり、物語が必要だと思った。
そこで思い浮かんだのが、映画「ショーシャンクの空に」「グリーンマイル」の美しく完璧な構成だった。
一ヶ月後、最終目標として提案された原稿用紙200枚には程遠く、10枚にも満たない短い原稿をMさんに送った。本の冒頭にある「ベランダ」というタイトルのものだ。
Mさんの反応は上々、いや、それ以上に感じられた。
「人が作ったもので、それに触れながら思考が拡散していったり 個人的な記憶がよみがえったりするのは すごく力のあるものだと思います」。
また、自殺を実行した部分に対しては「死にたいと思ったことがあるが実行できなかった自分としては、不謹慎だがわくわくしてしまうのも否めない」と。
この時の手応えが、その後の1年以上の執筆の支えとなった。
本の執筆スタイルとルーティン
毎月の締め切りまでにおよそ10枚の原稿を4つMさんに送り、感想を書いて送ってもらうというやりとりがルーティンとなった。
Mさんの感想は、最近観た映画や読んだ本、最近自分で考えたことなどを読んだ時の感覚にゆるく結びつけており、いつもとりとめがなく、どことなく雲のようにふわふわしていた。そのまとまらない感じが、物事を突き詰めて考えがちで何をするにもついつい小走りになってしまう私には合っていたようだ。よし悪しでジャッジされることなく自由に書けて、物語に膨らみを持たせることができた。
Mさんのスタンスは校正の段階に入っても変わらず、逆にこちらが少し心配になるくらい、「こうしたほうがいい」というようなことは言われなかった。
もちろん、文章的におかしなところや誤読の可能性のあるようなところはいつもの丁寧さで直してはくれたが、それ以外に関してはほぼ手が入ってないと言っても過言ではないくらいだ。
きっとガンガン赤が入ってくるものと思い込んでいた私は拍子抜けではあったが、書きたいもの・書きたくないものを尊重してくれる姿勢に深く感謝と信頼を感じた。
だが、執筆を終えた頃、Mさんが体調不良となってしまう。聞けばだいぶ良くないらしく、出版の企画自体の先行きも若干怪しくなってしまった。
体調の心配と同時に、ここまで来て、結局また振り出しなのだろうか、と落ち込むこともあった。まだわからないとはいえ、もしだめになってしまうとしたら、それはもうだめなのだから、仕方がない。今までだってそうだったじゃないか、と、半ばイジケも入りつつ自分を励ます。
人生、そんなに簡単にうまくはいかない。そういえば今年は大殺界だった。悪いことは皆大殺界のせいだ、と思うようにしたら少し気持ちが軽くなった。そう、成功も克服もない人生を肯定する物語を私は書いたのである。いざとなれば原稿を返してもらって自分で同人誌として出そうかな、などと思いつつ、Mさんの回復を祈った。
ほとんど諦めがつき、春、新しい仕事をどうにか見つけて働き始めた頃、Mさんから連絡があった。どうやら色々と大変だったようだが、「この本だけはどうにか出したくて」と言ってくださった。
発売日が決まり、入稿の締め切りが定められた。それからは兼業しているのもあって、あっという間の日々だった。
まとめ

本が出れば何かが劇的に変わるのだろうかと少し期待していたが、確かに忙しいものの、日常はそう変わりない日々が続く。ままならなさは相変わらずだが、生きるということは小さなハンマーで壁を掘り続けるようなことなのだろう。
変わったことといえば、SNSでエゴサーチして、本の感想を読むのが日課となったことだ。ほとんど毎日、何かしらの感想が上がっていて、救われる思いがする。あの日死ななくてよかったな、と心から思う。
願わくば「ショーシャンクの空に」のように、長く読まれる本になるといいのだけれど。