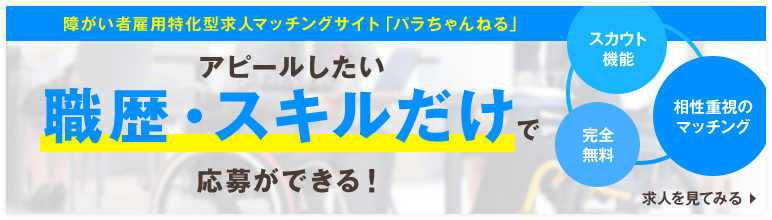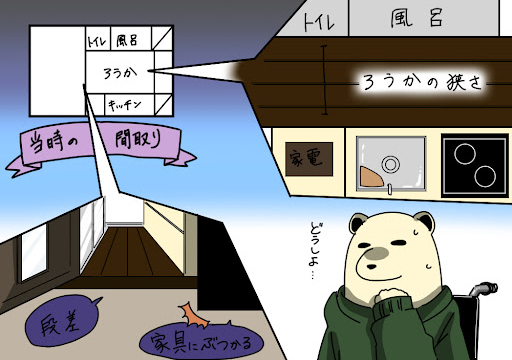僕には、生まれた時から脚の長さに左右差がある「下肢長不等」という障害がありました。今回は、コロナ禍における日本での病院探しが二転三転したときのお話をしたいと思います。
はじめに
こんにちは、しろくまです。
僕には、生まれた時から脚の長さに左右差がある「下肢長不等」という障害がありました。
幼少期にはさほど気にならなかったこの脚の左右差ですが、三十代手前になって急に違和感が大きくなってきました。悩んだ結果、僕は海外で手術を受けることに。
前回は、コロナ禍における隣国でのハプニングと、検査結果のお話をしました。
今回は、コロナ禍における日本での病院探しが二転三転したときのお話をしたいと思います。
地元の救急病院に駆け込む
海外で10ヶ月間、手術とリハビリを繰り返すも治療は思うように進まず。緊急帰国をした僕は、重度の感染症にかかっていることを知らされました。
日本では治療を引き継いでくれる病院がなかなか見つけられなかった僕は、ようやく隣国で治療ができそうな病院を見つけて二度目の渡航をしました。
そこで医師からは、保険のきかないこの治療には膨大な費用がかかると言われ、日本と比べておよそ倍に膨れ上がった治療費が払えるはずもなく、僕は隣国での治療が困難だと判断して帰国しました。
実家に戻っている時に脚の痛みが増したので、両親に連れられて地元の救急へと駆け込んで事情を説明し、応急処置をしてもらいました。それが、のちに今の担当となる医師Aとの出会いでした。
母と医師Aのやり取りから、初めは偽関節治療のプロだという医師が居る病院を紹介してもらうことになり、僕は生まれて初めて福島県へ向かいました。
一人で他県へ車椅子旅
両親との日程が合わなかったため、福島県へは僕一人で向かうことになりました。
海外と違い、言葉の壁もなく、車椅子の扱いも丁寧なのが日本クオリティー。プロペラ型の飛行機に乗って向かいます。
国内という安心感とともに、僕はこれまでの治療で何度も期待を裏切られ、いわば「期待からの急降下」を経験していたので、すっかり期待するということをやめてしまっていました。
「あまり期待しすぎずに、福島県へはちょっとした国内旅行の気持ちで向かおう」と考えていました。
空港からタクシーで病院へ直行し、採血をして、レントゲンやCTを撮って一日目は終了。

採血には毎回手こずってしまい、看護師さん達に申し訳ない…。
検査結果と診察は翌日とのことだったので、病院に隣接する滞在施設を予約してもらいました。本格的な一人旅状態で、施設内にあるレストランのハンバーグや野菜がとても美味しかったのを覚えています。
しかし、そんな楽しい時間も束の間。再び、現実の理不尽さと向き合う時間がやってきてしまいます。
理不尽な回答
「ご両親と来てね」
数名の医師に囲まれ、レントゲンを確認されながらも伝えられた言葉はたったそれだけでした。両親が仕事の都合で同行できないから、自分一人で飛行機に乗ってここまでやってきたというのに。
当事者である僕が一番知る必要がある問題であるにも関わらず、僕への説明は簡易的なものでしかありませんでした。福島までやってきたのも正直、骨折り損でした。
更に後日、両親二人がわざわざ福島まで赴き、同じ医師たちから話を聞いたのですが、話される内容は僕に対して伝えたものと大して変わりなかったそうです。
更に言えば、「この治療は難しすぎる。片足だけとかならまだしも、両脚となると摘出の金具も外国医師から送ってもらわないといけないし。」と、渋る医師がほとんどだったそうです。
その中で、一人の年配の医師(偽関節治療に長ける先生だそうです)だけが「何かあったら僕が聞きますからね」と言ってくれたそうなのですが、後日、僕の脚の状態が悪化して母親が電話すると…。

と、告げられたそうです。
自身の長年のキャリアに泥を塗りたくなかったのか、電話越しでは突然豹変したと母から聞いた時は愕然としました。
「(こんな人が本当に偽関節の権威なのか…?)」
腸が煮えくり返る感情がある一方で、諦めの気持ちもありました。
「(ほら、まただ。期待なんてするからもっと辛くなるんだ)」
自分を不幸だと思いたくない、認めたくない。人前では気丈に振舞っていたい。
期待するから辛くなる。だからもう、僕は何にも期待しない。
死ぬ時は死ぬ。自分が選んだ選択なんだから、誰を責めることもできない。もうやるだけのことはやったんだ。もがいたって仕方ない。
そんな思いから、諦めの境地に達してしまったのです。
この時から、日に日に僕の表情が暗くなっていったと、当時を振り返って両親や同居人が話してくれました。
長い治療の覚悟と新たな希望
そんな中、母が「治療を断られた」と、福島の病院を紹介してくれた地元の救急の先生に電話で伝えた時のことです。
電話を終えた母が、どこか安心した表情で僕の元へやってきて言いました。
「A先生がね、『これはご提案なのですが…僕でよければ、治療させてください』って言ってくれたのよ」
これが奇跡でないならば、何と言うべきなのでしょう。
これまでも、転機はありました。
けれど、何度も何度もすがってきた藁達も、結局は無意味でしかなかった。当時の自分を振り返るとすれば、その状況はまさに芥川龍之介の『蜘蛛の糸』の気分でした。
それでも、今、仏の慈悲によって目の前に垂らされている糸も、期待して登れば呆気なく切れてまた地獄に落ちてしまうのではないか。
僕はすっかり何かを信じることに対して怖がりになっていて、「お願いします」と伝えることも躊躇しました。
しかし、答えを渋っている時、僕の中でこれまでの出来事が走馬灯のように駆け巡る夢を見たのです。
記憶には、自分を支えてくれた家族や友人達が必ず近くにいてくれたこと。僕は、これが決め手となったのです。自分自身の問題である以上に、両親や周囲の人達をこれ以上不安にさせたくないという気持ちが勝りました。
長い治療になることは、脚の治療を行うと決めた時点で覚悟していました。順調にいかず、結局は遠回りで悪化してしまう状況にばかりなってしまったけれど。
「治る可能性のある選択肢の全てをやりつくした後でも、絶望はできるのだから」と考えを改めることにしたのです。
「よろしくお願いします」
母が自分の代わりに電話越しに頭を下げてA医師にお礼を言ってくれていた姿を、僕は今でも忘れることはありません。
灯台下暗しとはこのこと。こうして2022年に入ってようやく、地元での本格的治療が始まります。