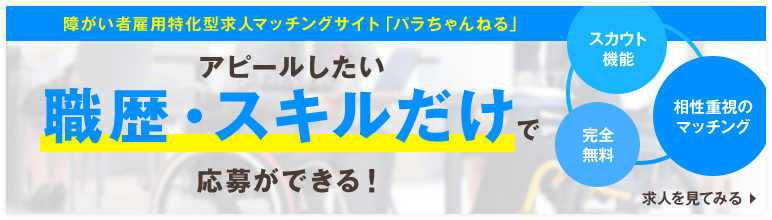16歳の時に飛び降り自殺を図り頸髄を損傷。以後車いすに。ここ最近の『おおいた障がい者芸術文化支援センター企画展 vol.3企画展「生きるチカラ」』への出展、「JR駅無人化反対訴訟」の第4回口頭弁論の傍聴という2つのイベントから感じた、「出来ない」からこそ生まれる「人と人とのつながり」とは?
現代の日本は健常者・障害者ともに生きづらい
今の日本社会は、健常者にとっても生きづらい。
経済は常に右肩上がりの成長をし続けなければならない。それも誰よりも早く。そのため、より効率的に合理性を持って生産し続けなければならない。そうでなければ淘汰される。
と私たちは思い込んでいる。
カール・マルクスは資本主義の本質とは「資本が無限に自己増殖する価値運動である」と説く。資本家はお金がほしいから事業を拡大するのではなく、際限なく増えようとするお金に自ら飲まれ、否応なく事業を拡大するしかない。だからいつまで経っても満足することがない。

前回の記事で私は、世の中を覆う資本主義の「経済性」「合理性」「効率性」の外側の世界へと行きたいと書いた。そんなオルタナティブな生き方の可能性を秘めているのが、障害者ではないのかと。
大分県立美術館の企画展で詩を展示していただいて感じたこと
10/27~11/7に大分県立美術館で『おおいた障がい者芸術文化支援センター企画展 vol.3企画展「生きるチカラ」』が開催された。
大分県内の障害のあるアーティストや鹿児島の福祉施設「しょうぶ学園」のアート作品を展示。12日間の会期で4000人近い来場があったそうだ。
実はこの展覧会に私も出展を誘われて、いくつかの詩を展示していただいた。
この出展の依頼を受けたとき、正直に言えば葛藤があった。私は障害があるから文芸をやっているわけではない。そもそも健常者の頃から本が好きで、創作活動を始めた。何も障害を負ったことが創作の動機でも、源でもない。そのあたりをよく勘違いされがちでうんざりすることが何度もあった。
だから「障害者」という括りの中でやりたくなかった。すぐに「障害があるのに頑張ってて偉い」などと言われてしまうからだ。
確かに指先には麻痺があるが、文章をパソコンで打ち込むのには大して困らない。むしろそこら辺の健常者に比べて打つのは早いほうではないだろうか。脳みそも正常だし、社会的な障壁があり最終学歴こそ中卒に甘んじてはいるが、一応県内一番、偏差値72の進学校に受かる程度には勉強ができた。少なくとも頭は悪くない。
だからこの私に「障害があるのに詩を書いてて偉い」とかいうやつは失礼であるということを自覚してほしい(なんか言われた)。
けれども、障害者になって12年が経ち、社会的な意味合いで確かに障害は私の一部となりつつある。
健常者の生きづらさと障害者の生きづらさはものが違う。私は、健常者の頃のほうが強く生きづらさを感じていた。
私は「障害者アート」を狭義の「アウトサイダーアート」として捉えることにし、障害自体に主軸を置くことはせず、社会的孤立や社会からの疎外感をテーマに考えた。立つ舞台は選ばなくとも、わかる人にはわかると信じて。
結果として出展してよかったと思う。というのも、純粋に展示されている作品たちがよかった。私は「障害者アート」という括りを内心馬鹿にしていたことを反省する。
ギャラリートークのために数日在廊していたが、なぜだろう、作品たちに囲まれていると力が湧いてくるのを身をもって感じた。他人に媚びず、評価を必要とせず、日々の地に足のついた暮らしの中で生まれた豊かで健全なるアートがそこにはあった。そう、「健全さ」を感じたのだ。まさに「生きるチカラ」だ。

裁判の傍聴で障害者の「出来ない」ことに対する強さを感じた
また、11月11日、大分地方裁判所で「JR駅無人化反対訴訟」の第4回口頭弁論があり、傍聴してきた。
※詳しくはnoteの記事を読んでください。
車いすユーザーが十数人、盲導犬を従えた視覚障害者、彼らを支援する介助者で傍聴席はひしめいた。
今回は弁護士による意見陳述のみで、法廷では原告の言葉は聞けなかったが、口頭弁論が終わった後に行われた報告会で聞けた。
原告である当事者のうち二名は、車いすを利用するだけでなく言語障害もある。
ひとりは脳性麻痺によって力を振り絞るようにゆっくりとしか話すことが出来ず、聞き取りは難しい。彼女の言葉を聞くために、会場に集った人たちは息をひそめて声に意識を集中させる。
もうひとりは気管切開をしているために声が出ない。寝たきりの状態で口に加えた棒で文字盤の文字を一文字ずつ示し、介助者が一文字ずつ読み上げていく。この聞き取りにも別の集中力がいる。
彼らの言葉に耳を傾けていると、私たちは不思議な連帯感に包まれていく感じがする。また、入廷行動のために垂れ幕を持って裁判所へ列をなして歩いたときも、同じように独特の連帯感があった。
傍聴の抽選のとき、裁判所の職員が「密になるので介助者の方は別室へ移動してください」というアナウンスに、私たちは顔を見合わせ、とある介助者が「常に介助が必要な人もいるんです」とはっきり告げた。
「出来ない」ことの力強さと言おうか、私たちは歩けず、喋れず、見えない者の集まりだったが、集まった障害当事者たちからは、自分たちが「出来ない」ということに対してむしろ誇りすら感じた。
それは彼らが彼らのまま社会を変えていける力を実際に持っているからだろう。ルールは遵守するためにあるのではなく、「共生のための相互尊重」のためにあるのだと、考えてみればごく単純なことを思い出させてくれる。
意志では本人でさえコントロールできない、体や命そのものとしての「生きる力」がまさにそこにある。
「出来ない」からこそ、コントロール不能の存在としての開き直りから生まれてくる理屈抜きの混沌、合理性も効率性も通用しない圧倒的な存在感、ある種の健全さが立ち上がってくる。
まとめ

「出来ない」ことが人とのつながりを、社会を生み出すのだ。
他人を否応なく巻き込んでいくエネルギーがある。それがないと生きていけないということもあるだろうが、逆に言えば、人に迷惑をかけてでも生きていくのだという、ふてぶてしいまでの覚悟と自尊心がある。
そもそも社会とは、生き物として未成熟なまま生まれてくる赤ん坊を守り育てるため、弱いものを生かすためにあるのではなかったか。
社会の行き過ぎた秩序やルールが人の生を抑圧し疎外し排除する。障害者という概念が生まれたのは産業革命後と聞いているが、障害者とは心身に欠陥を抱えている人のことでなく、資本主義社会の秩序とルールを押し付けられた結果、生を疎外され排除された人たちのことだ。
障害者の持つある種の「健全さ」とは、この社会において抑圧もコントロールもしきれない「欠陥」なのかもしれない。ならばこの欠陥こそが資本主義社会に打ち込み、新たな価値観をきりひらく楔なのではないかと私は思う。