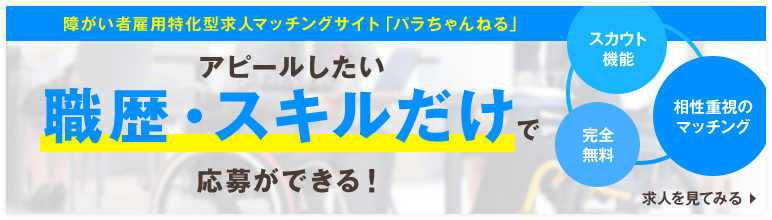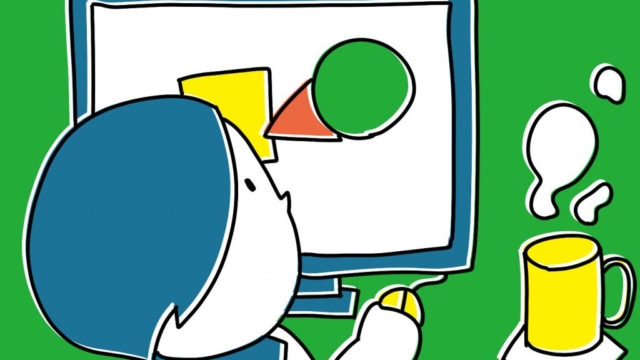16歳の時に飛び降り自殺を図り頸髄を損傷。以後車いすに。先日閉幕した東京パラリンピック。共生社会の実現がレガシー(遺産)であると言われていたが、運動音痴で陰キャな文化系重度障害者という立場から考えてみると、その違和感が拭えなかった。障害者全体とパラアスリートの違い、分断がそこにあるのではないか。
パラリンピックの81%問題について
先週末、東京パラリンピックが閉幕した。
レガシーとは遺産という意味で、「東京パラのレガシーは共生社会の実現」と、パラが始まる前から言われ続けていたことにずっと違和感を覚えていたが、最後までその違和感は消えることがなかった。
「81%問題」というものがある。
パラリンピック史上最大の成功と言われている2012年のロンドン大会後、「大会前に比べ開催後に障害者を取り巻く環境はどうなったか」と英国政府が調査を行ったところ、全体の81%が「とても良くなった」と答えた。
しかし、民間団体が同じ調査を障害当事者に行うと、59%が「変化がない」、22%が「悪くなった」と答えた。実に81%の当事者が、変化を感じず、むしろ差別が助長されたと感じることも少なくないと言うのだ。
これは一体どういうことだろうか。

ロンドン大会では障害者を「スーパーヒューマン(超人)」とPRし、熱狂を生んだ。これは「共生社会の実現」とはベクトルが異なる。むしろ真逆と言ってもいいかもしれない。
スポーツでメダルを争うということにはそもそも能力主義や個人主義の思想がついてまわる。メダルをたくさん獲ろう、メダルの価値を上げようとすれば、必然的にその思想は強化されるだろう。
何も能力主義が悪いわけではない(とは言ってはみるが、私は健常者の時、能力主義をこじらせて自殺未遂をしたので、未だ私の頭にこびりついているそれに対してとても懐疑的になっている)。
むしろ障害者にだって頑張れる機会はほしい。障害者だからと差別され、そもそも競争のスタートラインにすらなかなか立たせてもらえない身にしてみれば、パラリンピックというものがあり、それにエントリーできる人がおり、多くの人たちに認知され、興味を持ってもらえることはいいことのように思える。それによって障害者雇用も進んだ部分もあっただろう。たとえパラが終わりその契約が打ち切られようとも、少なくともなんらかの跡を遺せたかもしれない。能力のある人ならそれをきっかけにしてどうにか生きるすべを見つけるだろう。
しかしそれは「共生社会」ではない。前にも書いたが、パラリンピックにエントリーできるのは身体障害者(聴覚障害者は除く)と一部の知的障害者だけだ。すべての障害者に機会が与えられているわけではないのだ。
ロンドン大会が選手以外の障害者のスポーツ参加への動機づけにもならなかったというデータもあるらしい。作り上げられたパラアスリート像と実際の生活をしている障害者との分断を感じてしまう。
ロンドンパラリンピック競技大会の弊害

ロンドン大会によって「スポーツをしない障害者は頑張っていない」と世間から見られてしまう風潮が生まれてしまったと、とある元パラリンピアンは言っていた。東京2020が決まって以来、日本で同じことが起きないようにと議論を積み重ねてきたのだと。
長年パラスポーツに身を捧げてきた彼の中に渦巻く葛藤を見たが、それでもやはり、私たちの目に触れるメディアはどうしても「弛まぬ努力」「困難を乗り越える」「障害を克服する」「支援者への感謝」といった切り取り方をしがちだ。
そして障害者をよく知らない人たちはこう思ってしまわないだろうか。「障害者でも頑張れば困難を乗り越えられる」「困難を乗り越えられない障害者は怠け者だ」「感謝のない障害者は傲慢だ」と。
それは障害者の個人の努力によって健常者へと近づくべきだという時代遅れな「個人モデル」の在り方だ。そういう健常者による健常者に心地のいい安易なレッテル貼りが障害者間の格差を生み出す。健常者受けのいい障害者とそうでない障害者の差が広がっていく。それとは真逆である、障害は社会の側にあるという「社会モデル」こそ「共生社会」実現の礎なのに。
まとめ

どうすれば共生社会が実現されるだろう、と考える。
パラリンピックは出会いのきっかけに過ぎない(というか、パラリンピックは共生社会の実現をレガシーに掲げるべきではないのではないか、とさえ思っているが)。パラアスリートは美学を持って生きるアスリートなのであって、障害者の代表ではない。普段の生活に当たり前のように障害者がいるべきだろう。
世界人口の約15%の人が何らかの障害を抱えているのだという。100人中15人というと多く感じはしないだろうか。それほど普段、障害のある人と健常者との断絶があるということだ。
パラバブルは崩壊していくだろうが、できることなら障害者がこれからもメディアに出続けていてほしい。働き続けてほしい。パラスポーツに興味を持った人たちがこれからも関心を抱き続けていてほしい。イベントが終わったら手のひら返しのやりました感の演出では結局何も変わらない。
かわいそうな人でも超人でもない、ただの人である障害者と普通に付き合う、それが当たり前になることを望む。