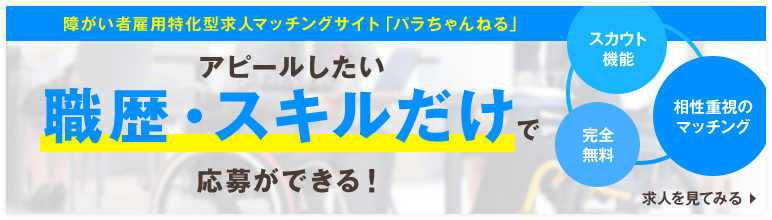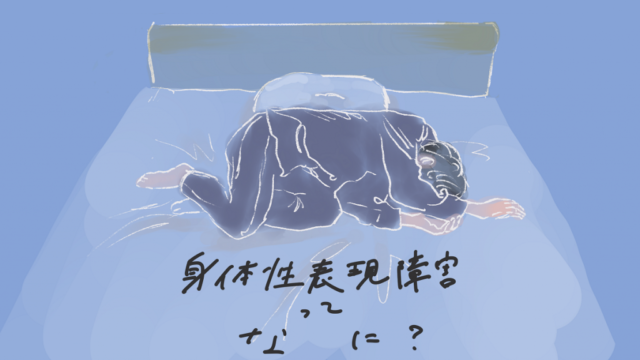16歳の時に飛び降り自殺を図り頸髄を損傷。以後車いすに。9月16日に「しにたい気持ちが消えるまで」という書き下ろしエッセイを出版した。実は「30歳までに商業出版で本を出す」という密かな目標を20歳の頃から抱いており、現在29歳なので、ギリギリ目標を達成してしまった。今回は出版社からお声かけいただいたところまでを振り返る。
子供の時から物語が好きだった
何にも思い通りにならなくて、一度は自死を選ぼうとし、ベランダから飛び降りた私だが、思い通りにならない日々の中でも、小さなハンマーでポスターの裏の壁をこつこつ掘るみたいなことをしていたら、ご褒美めいた瞬間が訪れることもあるらしい。
「ショーシャンクの空に」という映画史に残る名作がある。原作はスティーヴン・キングの小説『刑務所のリタ・ヘイワース』。監督・脚本はフランク・ダラボン。
公開当時、興行収入はまったく振るわなかったらしい。だがその後アカデミー賞のノミネートや口コミによって1995年には最もビデオレンタルされた映画作品となり、公開から30年以上経った今でもさまざまな映画ランキングの上位に必ずと言って良いほど君臨している。私ももれなくこの映画が好きだ。
元々はスティーヴン・キングを本読み友達である紅茶屋のマスターから勧められ、小説を読んでいたが、映画化されているものが多くあることを知り、今はもうなくなってしまったスクリーン&BOOというレンタルビデオショップでDVDを借りて観ていた頃があった。
監督によって脚本が原作通りだったりそうでなかったりと、比べるのも楽しい。キング自身が制作総指揮を担ったものもあり、キューブリックの撮った「シャイニング」が気に入らずに自ら監修して撮り直したという逸話があるのだとか。
中でも、フランク・ダラボン監督によるキング作品の映画は脚本が素晴らしく、まず、原作に忠実であり、原作以上に物語として練られていて、3時間以上の長尺であっても息もつかせぬ面白さだ。優しい眼差しとユーモア、程よい毒っけ、美しい構成。観客にフラストレーションを溜めまくった挙句のカタルシスが快感でたまらない。映画の中で雷が鳴り出すと、どうにも興奮してしまう。
子供の時から物語が好きで、小説や漫画、映画やアニメなど、自分で楽しむのはもちろんだが、友人とそれらを分かち合うのが何よりも楽しかった。良い作品を見つければすぐに勧め、どうだった?と感想や考察を述べ合った。
そういう楽しみがありながらも、16歳のときに3階アパートのベランダから飛び降り自殺を図って失敗、重度の身体障害者となってしまったが、その後も物語が好きなのは変わらない。
商業出版で本を出す夢が叶った

9月16日に三栄という出版社から「しにたい気持ちが消えるまで」という書き下ろしエッセイを出版した。
実は「30歳までに商業出版で本を出す」という密かな目標(というか夢というか)を20歳の頃から抱いていた(現在29歳なので、ギリギリ目標を達成してしまった)。
10年くらい前、本読みのマスターのところで紅茶を啜りながら、ふと、「文筆で食べていけないだろうか?」と世迷い言をこぼしたところ、マスターはそんな私を馬鹿にしたり現実を見ろと諭したりすることなく、「書きなさい」と言ってくれた。
重度の身体障害者として車いすでひとり生活する私にとって、文章を書いてどうにか食べていけないか、というのは、大きな夢でありながら、とても現実的な手段でもあった。
いわゆる”親ガチャ”で大きくハズレを引いてしまった私が生活で頼れるものは、障害者向けの行政サービスと障害年金だけ。どれだけ真面目に就活をしても、中卒の女性の重度障害者が働ける職場なんてない。最悪、生活保護を受給して暮らすか、施設に入るかを覚悟した。
多くの障害者仲間が生活保護と年金で細々暮らしている。だから自分もそうなることはしょうがないよなあ、と思いつつも、どうにか足掻きたい。最低限度以上の暮らしがしたい。唯一私にできそうなことが、書くことだった。
22歳に本を書き始めたが最初は食べいけるほどではなかった
まずは手堅く新人賞を獲ろうと原稿用紙200枚を越える小説をなんとか書き上げたのは22歳の頃。
運よくとある新人賞の最終候補に残るも、当時まだまだ無意識に作品を描いていた私は、審査員の先生方の批評に耐えきれず、掲示板での実名を挙げた悪意ある書き込みも相まって、てんで書けなくなってしまった。
他にもチャレンジする方法は色々あったのだろうが、あっさりと心を折られてしまった私は、その後新人賞の最終候補に残ったおかげでたまたま得たテレビの仕事で、思いがけず才覚を発揮し(と思っていたけど、よくよく考えてみれば、当時は東京パラリンピック前で、「障害者バブル」といったような現象が起きていた)、しばらくはテレビの仕事でどうにか食い繋いだ。
創作は続けてはいたが、食べていけるほどの収入にはつながっていなかった。確約はないにしろ、もしかしてこのままテレビでどうにかやっていけるんじゃないか?と甘い見通しが運の尽きで、世界中にコロナが蔓延、テレビの仕事は一切なくなり、元の先行きの見えない暮らしに戻った。
たまたま知り合った男性と恋仲となり、恋の熱に浮かされたのもあって、これはもう結婚しかないと盛り上がっていたところで振られてしまい、再び振り出しへ。
「障害者としての私」以外にも文学があるという想い
どうしたものかと思っていたところに、お世話になっていたTVプロデューサーからリモートでのテレビ出演のお声がけが。内容は障害者バラエティ(※バリバラではない)だと言う。
今まで、ニュースやドキュメンタリーなど、ちょっとかしこまった感じの真面目なものばかりに出演していた。バラエティ番組は経験がない。なんか面白そうなちょっとエッチなネタがない?と飲み会のノリで聞かれる。ないことはないし、むしろ自分では結構面白いと思っている持ちネタがあった。
あまり視聴率は高くないとはいえ全国放送で実体験に基づいた下ネタを披露する、ということに地元の仲の良い知り合いたちは難色を示し、そこまでする必要はないんじゃないの?と諌められた。私は身を切り売りしているのだろうか?と真面目に考えてみた。そもそも車いす当事者として語る、なんてまさにそういうことではないのかと悩んだこともあった。社会に対して差し出せるものが「障害者としての私」だなんて嫌だ、と。
資本主義にしっかりと絡め取られ、何もかもを剥ぎ取られた素っ裸なマイノリティとして道化を演じ、束の間に消費される?
いや、そんなことはない。私は消費されない。なぜなら、私には文学があるから。自分でもちょっと笑ってしまうが、わりかし本気で思った。
まとめ

自分のことを語る時、「赤裸々だ」と言われることがある。が、どうにも私はピンとこない。私にとってそれはすでに普遍性を伴った語るべき物語になっていると思うからだ。これは大義名分をこしらえているだけだろうか?フロムの「疎外」という言葉が頭をよぎる。
でも、何にせよ、私はフロムのいう「成功のみを追いかける疎外された社会」の中で暮らしている。それならばその中で、成功とは程遠い所にいる私が小さな棘や毒を持っておどけてやろうじゃないか。
テレビ番組に何度も出演する中で常に考えさせられたのは、「視聴者に対していかに印象に残れるか」だった。
それは私自身もだが、番組自体もそうで、出演前に配布される番組構成はいつも勉強になった。その番組の中でどれだけ素晴らしいことが語られるとしても、観てもらえなければ意味がない。伝えるには、ただ伝えればいいのでなく、伝わらなくてはならない。途中で飽きられたり、観るのがしんどくなってしまったりしてはだめだし、難しすぎてはいけない。毒にも薬にもならないのでは伝える意味がない。
番組は平日の夜8時からの放映だった。毎日学校や職場でストレスにさらされ、くたびれはてた人が何気なくテレビをつけてご飯を食べながらぼーっと観る。そんな人に何かを伝えるなら、どんな伝え方がいいだろう。
笑えたりホッとしたりちょっといい話だったり。それに文学的な深みがあればなおいいのではないか、と思った。そこで実際に語ったこと以上のことが伝わるような、観た人がそこからさらに自身の想像の羽を広げられるような。
結果として、その番組は好評だった。それまでで一番SNSで反響があった。
その時だ、三栄の編集の方から「本を出さないか」と連絡があったのは。今から約2年前のことだ。