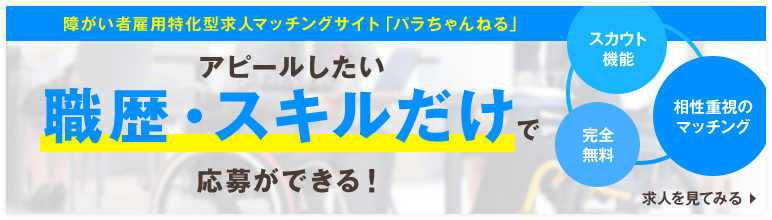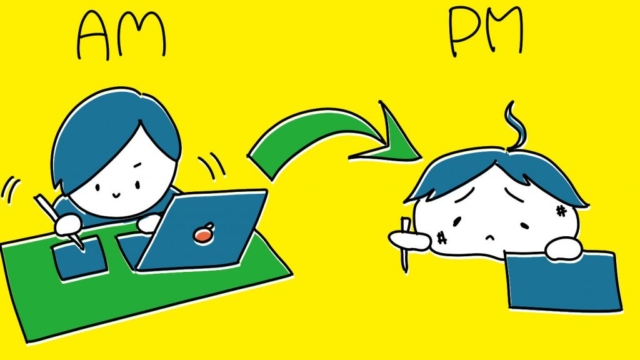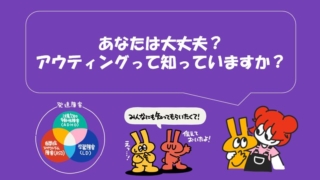16歳の時に飛び降り自殺を図り頸髄を損傷。以後車いすに。振り返ってみると、飛び降りた後よりも、飛び降りる前、健常者の頃のほうが生きづらかった。生きづらさを感じるのは、自分が思い込んでいる理由ではないのかもしれない。自分の生きづらさは、どこからやって来ているのか。
生きづらさの考察
自殺未遂をした結果、障害者になってしまった人間としては、「生きづらさ」というものについて考えざるを得ない。
どうしてあんなことをしてしまったのだろう? と、ふと立ち止まって考える。
後悔からではなく、そのときの自分のことを客観的に分析したいという興味からだ。
間違いなく言えることは、障害者になった飛び降りた後よりも、飛び降りる前、健常者の頃のほうが生きづらかったということ。
それはなぜなのか。一般常識から言えば、健常者よりも障害者のほうが生きづらいに決まっている。
けれど私は逆なのだ。
ただの強がり?そうではない。現に今の私は「死にたい」なんて思わない。
健常/障害は関係なくて、ただ若かったから、若気の至りで死にたかったのだろうか?性格の問題だったのか?社会的な要因があるのか?などなど、自問自答は尽きない。
なかなか、面倒くさい性格だな、と自分で思うが、この記事がなにかの参考になればと思う。

盲目の友人Z君とのランチ
盲目の友人Z君がいる。鍼灸師兼噺家として活動する若い男性だ。
ある晴れた日曜日。原稿に行き詰まった私は彼とランチに行く約束をした。
Z君は全盲であるが歩行訓練を受けており、自宅から近所の駅までは白杖をふりふりしながら自力で歩くことができる。
私も、えっちらおっちらと車いすを漕いで駅まで行く。道のりは普通の人なら殆ど感じないほどだが緩やかな上り坂になっており、普段引きこもり生活をしていて体力のない私にはちょっときつい。
運動不足を実感しつつ、起立性低血圧でクラクラしながらものろのろ漕いでいると、ちょうど知り合いのおじさん、Aさんに出くわす。
彼は副業でヘルパーをやっている。これ幸いと駅まで車いすを押してもらうことに。聞けば暇をしているようで、三人で食事をしないか誘う。
私がZ君を誘導しつつ車いすを押してもらうことは出来るが、誰か介助者がいてくれたほうがより楽ちんだ。Aさんは快諾してくれた。
Z君と合流し、私はAさんに車いすを押してもらい、Z君はAさんのベルトを掴んで歩く。よくよく考えてみればなかなかシュールな光景だが、そんなことは微塵も気にならない。
天丼が有名で観光客にも人気なお店へ入る。Z君にメニューを音読してあげ、運ばれた料理の中身や位置を説明する。すると彼は指先や箸でつんつんしながら普通に食べることができる。
幸せと不幸は他人が決めるものではない
生まれつき弱視だった彼に、生きづらさに障害は関係あるかと聞いた。関係ない、と彼はきっぱりと言う。
「香川の大島青松園に行ったんだ。ハンセン病患者の療養所だね。資料館を見て回ったんだけど、差別され、人目の触れない中に隔離されても、彼らは彼らなりの幸せを感じることもできたみたいだよ。もちろん苦しみはあっただろうけど、それでも生をまっとうしてる。彼らはハンセン病になったから生きづらく不幸になったのではなく、ハンセン病を理由に差別され隔離されたから生きづらく不幸になったんだと思う。障害と生きづらさとは、直接的には関係ないと思うな。幸か不幸かは、他人が決めるものではないから」
そんな話をしてくれた。なるほど、確かにそうだ。
神谷美恵子の『生きがいについて』にも、そのようなハンセン病患者らの生活のことが書かれていた。社会からの理不尽な仕打ちに苦しみ、悲しみながらも、それでも心の内の自由を見つけて暮らす人もいた。
「それに、ここ何十年かで、障害者の差別や偏見は随分となくなったと思うんだ。僕が子供のときは、身内に障害者がいるなんて知られたくないって感じだった。祖父母にさえ知られたくない、みたいな」
視覚障害が悪化し全盲に
Z君の障害は彼が大学生のときに悪化して全く見えなくなってしまった。適切な治療を受けなかったからだという。もっと早く治療していれば、せめて全盲になることは避けられたのかもしれない。けれど、そうしなかった。
それは、自らが視覚障害者だということを家族共々受け入れてなかったかららしい。
彼の両親は自分の子供が障害者であるということを認めたくなかった。誰にも知られたくなかった。
そういう教育の中で育った彼は、あくまで健常者として高校、大学と進学した。
出身高校は県内でも有数の進学校であるが、出されたプリントはすべて自分で拡大コピーをして使っていたらしい。成績は芳しく無く、暗黒時代だったと語る。
私も似たような進学校に通っていたが、健常者でも授業についていくのが大変なのに、加えてハンデがある中、なんの支援もなく皆と同じ学校生活を送っていたなんてむしろ尊敬する。
手帳取得と支援を受けた結果
大学を出た後は就職先もなく、実家に引きこもった。
当時2012年。世には総合支援法があり、いろいろな支援がすでにあったのに、そのどれにもたどり着けていなかった。支援があると知ったとき、彼は驚き、どうして誰も教えてくれなかったのかと思ったのだという。
とはいえ最初は自身を障害者と認めることに抵抗があった。障害者であることを人に知られたくない。そういう教育を受け、差別を自身の心に内在化させていたからだ。
しかし、見えないことは隠しようがない。自分じゃどうしようもない。
「障害者であることを人に知られたくない」なんておかしいし、そんなことは無理だと気がついた彼は、手帳を取得し、支援を受け、仕事を得て一人暮らしを始めた。それから視覚障害は彼にとっての生きづらさではなくなった。

目に見えて分かりやすい困難を抱えていると、支援を得られやすい。
これは普段車いすに座って生活している私もそうだ。歩けないので、障害者であることを隠しようがない。手帳を取得することに私は抵抗を感じなかった。
Z君も結果的には、障害を受け入れないとどうしようもないというところで折り合いがついている。私たちは身体障害者一級であり、年金など公的サービスを手厚く受けられる立場にある。
彼が感じていた「生きづらさ」は、障害を受容することで無くなった。
これは、彼の内なる差別心と決着がついたことで生きづらさに名前が付き、対処としての適切な支援を得られたことによる。
まず個人が生きづらさを抱えた状態があり、それを本人が認め、他者に認めてもらい、具体的な支援を得て、生きづらさが解消されている。
生きやすさを得るための諦め
「周りが当たり前にできることが自分には出来ない」のを自分自身が認めるのは、精神的な辛さがある。認めるということは諦めるということだ。
この「諦め」こそが、生きやすさを得るために必要なことではないだろうか。諦められず、けれどうまく出来なくて「葛藤」している状態は苦しい。
たまに勘違いした人が、「いつか歩けるようになるかもしれない、諦めずに頑張って」と言ってくる。
私は一生歩けないことを十分受け入れているのだ。むしろ歩くことを諦めないことほど、酷なことはない。「頑張って」「努力して」なんとかなることではないのだ。
Z君も私も、この身体で一生生きていくために乗り越えていることとはいえ、Z君は「付き添いなくふらっと散歩して、道行く誰かに気軽に声をかけてみたいな」とふと漏らすことがあった。
私も、時に、ひとり自転車に乗って街を散策してみたい欲求にかられることがある。しかしこれは例えるなら健常者が「空が飛びたい」と言っているのと変わらない。
そんな夢を見ることは構わないが、実際に羽が生えてくるわけでもなし、どうしようもないことだ。飛べないことに落ち込むよりも、他にできることで十分楽しめるのだから、そちらのほうがいい。